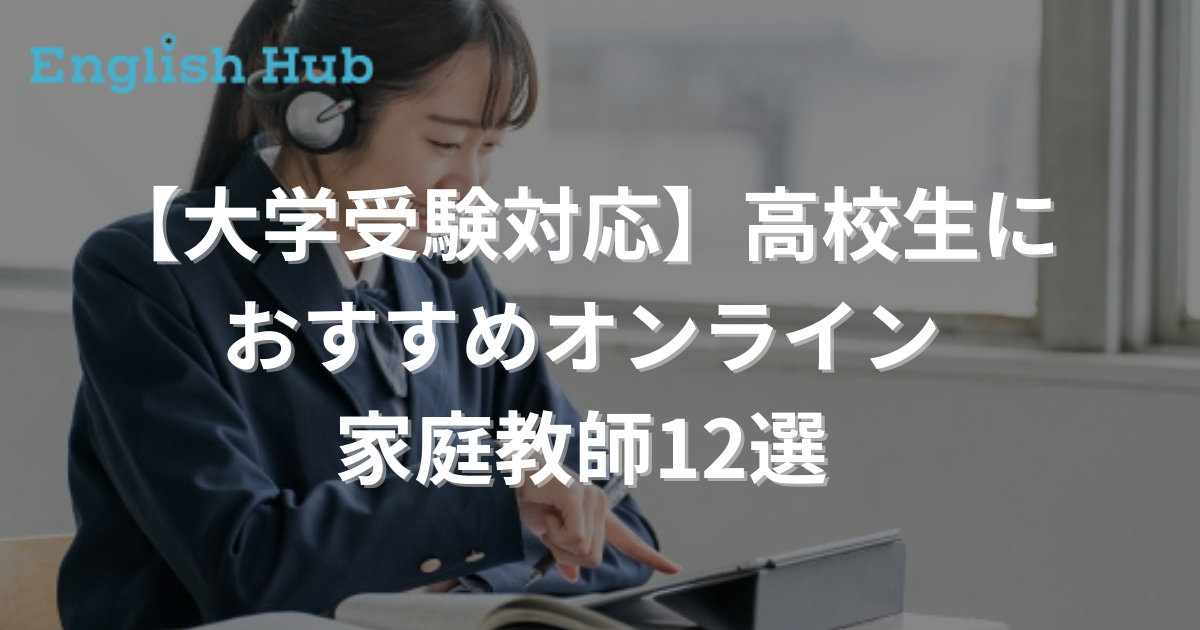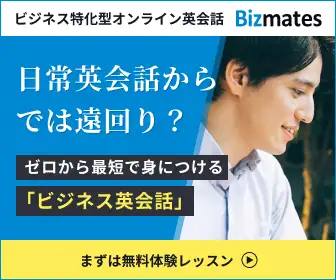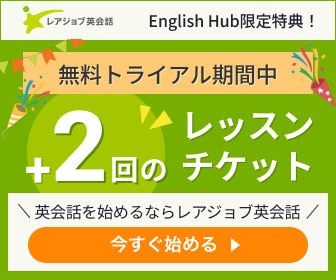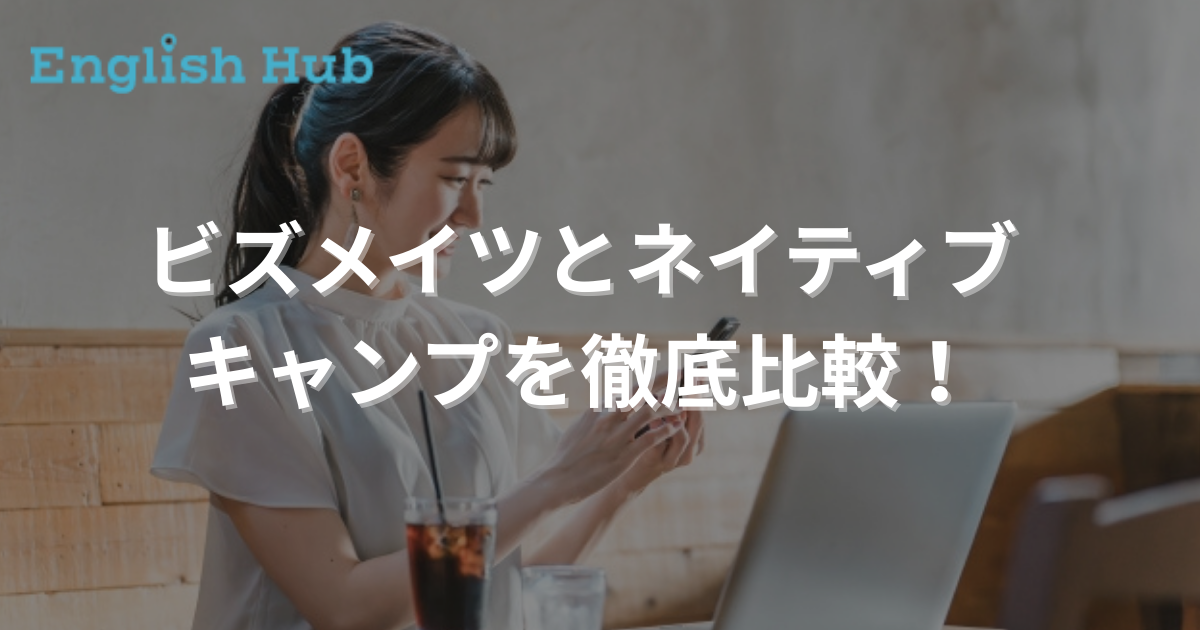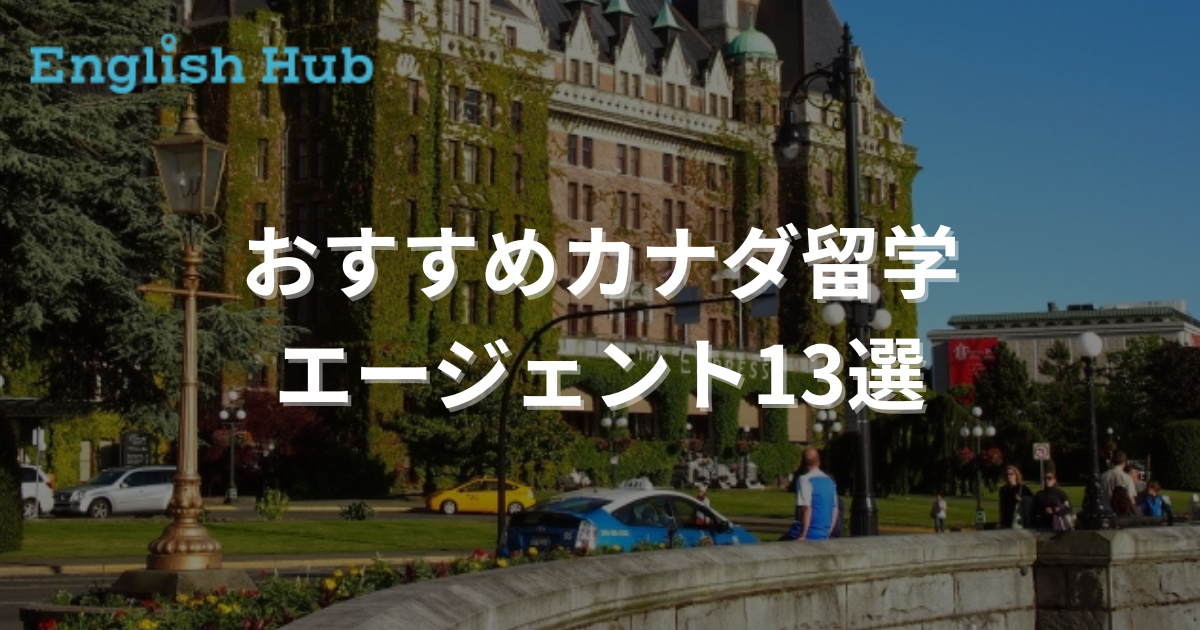TOEICを学習されている方の中には「Part6は、Part5やPart7と毛色が違うので解き方がわからない」「Part6の攻略法が知りたい」と感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回はTOEIC Part6のおすすめ攻略テクニックについて詳しく解説したいと思います。
※この記事では、2016年5月から導入されたTOEIC新形式に対応する内容を解説しています。
TOEICリーディングセクション・Part6(長文穴埋め問題)について
TOEIC L&RのPart6は、長文穴埋め問題です。
Part6では文章が4題あり、1題の文章につき空所問題が3題、文の挿入問題が1題あります。Part6の問題数は全部で16問です。選択肢は1題につき4つ用意されています。
TOEICリーディングセクション・Part6の対策&コツ
1. 文章の流れを意識しながら全文を読む
Part6は長文中にある空所の穴埋め問題であるため、「文章全体を読まず、空所の前後だけを見ても解けるのではないか?」と考えている方も少なくないのではないでしょうか。
2016年からのTOEIC新形式の導入以降、従来のPart6では無かった文章の挿入問題が追加されました。
挿入問題を解くには、文章全体の流れを意識し、内容を理解することがポイントになります。挿入箇所の前後で話されている内容や展開の流れを掴んだうえで、自然な文章を空所に当てはめる必要があるためです。Part6に挿入問題が追加されてから、より一層文章全体の流れを把握しながら読んでいく必要性が高まりました。
挿入問題以外の問題に関しても、正しい選択肢を選ぶための情報が文章内の複数箇所にわたって示されているケースが存在します。このような問題では、空所の前後や空所を含む文だけを読んで選択肢を絞ると、間違った解答を選んでしまう可能性があります。
Part6でスコアアップを狙うためには、文章の流れを掴みながら、空所の前後だけでなく全ての文章をしっかりと読むとよいでしょう。
2. 文脈に依存する問題は後回しにする
Part6には、独立型問題と文脈依存型問題の2種類があります。
独立型問題とは、文章の内容に解答が左右されることがなく、空所の前後から判断して解答することができる問題です。一方で、文脈依存型問題とは、文章内の話の展開や、前後の文脈を理解したうえで解く必要のある問題です。
Part6を解く際のポイントは、独立型問題であれば空所前後から判断して選択肢を選び、文脈依存型問題であればそのまま読み進めて後から空所に戻って選択肢を選ぶように、空所部分まで読み進めたときに、臨機応変に対応することです。
例えば以下のような問題は、文全体の内容と展開を理解してから答える必要があるので、空所前後のみで選択肢を選ばずに文章の全体像を把握してから解くとよいでしょう。
…… For that reason, we are urging experienced project leaders to attend each one of the interactive seminars that will be held throughout the coming month. _______.
※空所前後のみ抜粋
(A) Let me explain our plans for on-site staff training.
(B) We hope that you will strongly consider joining us.
(C) Today’s training session will be postponed until Monday.
(D) This is the first in a series of such lectures.
上記の例題は、従業員を対象としたトレーニングセッションを開催するにあたり、経験豊富な社内のプロジェクトリーダーの参加を求める内容となっており、(B)が正解です。
その他の選択肢にも、“training”や“lectures”などのキーワードが散りばめられているため、一見関連があるようにも見えますが、プロジェクトリーダーへ協力を依頼する背景を説明したあと、最後の文で今一度参加を促す流れが最も自然であることを考えると、適切な答えは(B)のみに絞り込まれます。
このように、文章の挿入問題では、空所に当てはまる適切な文を見極めることが求められるため、文章全体の内容を理解し、話の流れを掴んでから解く必要があります。
一方で、語彙問題や定型表現問題、品詞問題などは、基本的には空所の前後を見て解くことができる独立型の問題です。
Part6では、空所に差しかかったときに解答するための根拠がまだ足りないと思ったら、手持ちの情報だけで解答を選択したり、迷って時間を消費したりするのではなく、文をさらに読み進めてから再び保留した設問に戻って答える判断をすることが大切です。
3. Part5とPart7の両方の読み方を意識する
Part6は、Part5とPart7をミックスしたような問題です。Part6の英文を読む際は、空所の前後はPart5を解く時のように注意をしながら正確に読み、空所の前後以外はPart7の長文を読む時のように素早く読み進めることを意識するといいでしょう。
Part6を読み進める際の姿勢として、Part5とPart7の文章を読む時の両方を意識すると効果的です。
TOEIC Part6のスコアアップに効くおすすめトレーニング法
Part6のスコアアップに有効なおすすめトレーニング法は音読です。
Part6の問題を解いたら、分からなかった単語や文の意味を確認し、文章の精読を行うことをおすすめします。精読では疑問点を全て解消し、文の内容をしっかり理解するようにしましょう。精読をした後は解説をよく読み、正解の選択肢が正しい根拠と、不正解の選択肢が間違いである理由をしっかり確認するとよいでしょう。
その後は、構文や内容を意識しながら音読を行うと効果的です。音読をすることによって、英語を英語の順番のまま理解する力を培うことができます。
前述した通り、Part6はPart5とPart7をミックスしたような問題です。Part7の長文読解や、Part5の対策をしっかり行うことがPart6のスコアアップにも繋がります。
まとめ
いかがでしたでしょうか。今回はTOEIC Part6のおすすめ攻略テクニックをご紹介しました。Part6はPart5とPart7を混合したような問題形式です。Part5やPart7対策の学習を積み重ねた効果が現れやすいパートでもあるため、Part5とPart7の対策をしっかり行うことと、Part6の解き方を学ぶことがポイントです。Part6でスコアアップするために、ぜひ今回ご紹介したテクニックを参考にしてみてはいかがでしょうか。
佐藤 千嘉
最新記事 by 佐藤 千嘉 (全て見る)
- ゲーム感覚で英語学習ができるおすすめアプリ6選 - 2026年1月15日
- 【TOEIC頻出】品詞を誤りやすい要注意英単語15選~前置詞・接続詞編~ - 2025年12月1日
- TOEIC頻出!「自動詞と間違いやすい他動詞」11選 - 2025年12月1日
- 英語コーチになるには?コーチングの副業や求人サイトの情報も - 2025年11月30日
- 英検対策におすすめの単語帳6選【5級~1級対応】 - 2025年11月1日